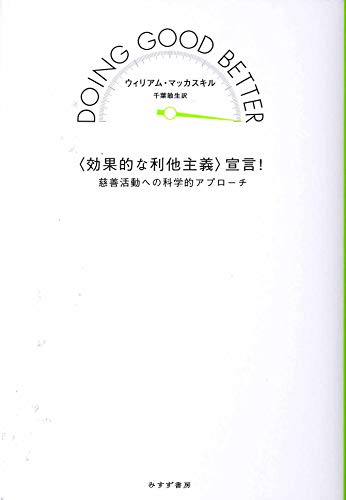世界をより良くするために、ズッコケ三人組について語る(主に「ズッコケ文化祭事件」とそのパターナリズムについて)
ふと、もうちょっとみんな「世界をより良くしよう」みたいなことを考えてもいいのでは?という不満を抱いた。他人に不満を抱く前にまず自分が実践しようとおもったので、ズッコケ三人組について語ろうと思う。ズッコケ三人組について語ると世界がより良くなるのは自明のことなので。
語るまでもないと思うが、「ズッコケ三人組」は那須正幹作の児童文学作品である。小学6年生(たまに5年生)の、小柄で色黒、頭は悪いが運動神経抜群で行動力の塊な「ハチベエ」、読書の虫で博識だがプレッシャーに弱くてテストの成績は悪い「ハカセ」、気弱な巨漢だが優しくて人懐っこい「モーちゃん」の仲良し三人組が、株式会社を設立してみたりタイムスリップしてみたり親の離婚で疎遠になった父親に邪険に扱われたり、はたまた修学旅行を楽しむだけだったりする幅広な作風で、50巻も刊行された大ベストセラーシリーズである。大人向けの続編として「ズッコケ中年三人組」シリーズも刊行されている(2015年に完結済み)。
残念ながら作者の那須先生は今年の7月に亡くなられたのだが、その訃報に先々月気づいたことがきっかけで、猛烈にズッコケ三人組を読み返したくなった。実家には何冊かあるはずなのだが、このコロナ騒ぎでいつ帰省できるとも知らないため、「ズッコケ文化祭事件」の電子書籍を購入した。シリーズを熱心に読んでいた小学生の頃も文体が大人っぽいところを気に入っていたのだが、改めて読んでみると、ちょっと表現が平易なことを除けば想像以上に一般的な娯楽小説と変わりない内容だった。何より、その「子供を舐めていない」姿勢が想像以上のものだったことに衝撃を受けた。児童書籍ゆえに文章量こそ少ないものの、大人が読んでも十二分に楽しめる内容であるため軽い短編を読みたい人や徳を積みたい人は買うべきである。今回紹介する「ズッコケ文化祭事件」のほか、「花のズッコケ児童会長」「うわさのズッコケ株式会社」「ズッコケ結婚相談所」「参上!ズッコケ忍者軍団」あたりが特におすすめ。
以下、「ズッコケ文化祭事件」の感想。数十年前に刊行された作品のためネタバレは一切気にせずに書く。ネタバレが気になる人は買って、読んで、世界をより良くしてから以下の文章を読んでほしい。
まずあらすじ。
----------------------------------------------------------------
文化祭で創作劇をやることになった3人組のクラス。とにかく目立ちたいハチベエは、実家の八百屋に客として出入りする市内唯一の文化人にして児童作家である新谷さんに脚本を依頼し、あわよくば自分をいい役につけてもらおうと画策する。クラスメイトの賛同も得て新谷さんに脚本を書いてもらうことに成功するも、その脚本「トンカチ山の大魔王」の内容は幼児向けの童話チックな内容で小学6年生の劇としてはあまりにも幼稚であった。案の定クラス内では大不評。相談の結果3人組のクラスは、「トンカチ山の大魔王」を原型をとどめないほどに改変した「アタック3」(内容は暴力団との抗争劇)を上演する運びとなった。「アタック3」は本番で大成功を収めるも、自分の書いた脚本を無断で跡形もなく改変された新谷さんは激昂する。そんな新谷さんの家に3人組の所属するクラスの担任、タクワンこと宅和先生が謝罪しに向かう・・・
----------------------------------------------------------------
「ズッコケ文化祭事件」はシリーズでも異色の作品である。なんだかんだシリーズのほとんどの作品では主人公の3人組が物語の中心となって活躍するのだが、本作では主人公と言うよりも狂言回しとしての側面が強い。脚本がらみの紆余曲折はあれど、彼らはごく普通に文化祭の劇にとりくんで、ごく普通に試行錯誤し、ごく普通に成功するだけである。
ハチベエは「アタック3」でも敵の親玉役という美味しい役を演じることに成功するし、文化祭に興味のなかったハカセは徐々に裏方としての楽しみにのめりこんでいって大活躍する。モーちゃんに関しては本作ではただただ影が薄い。文化祭の劇に向けてクラス内でワイワイと取り組む描写は非常によく描かれており、そのあるある感も含めて大変楽しいのだけれども、明らかに3人組より焦点のあたっている人物が別にいる。その1人はもちろん児童作家の新谷さんだ。
本作における新谷さんの描写は詳細で、そして非常に辛辣なものである。市内唯一の専業作家として華々しくデビューしたまではいいものの、その後はスランプに陥って数年間1冊の本も出せずに現在の生活は妻の収頼り。親切心で書いた劇脚本は小学生からボロクソに酷評される。自身の主催する童話サークルで自作品を批評されれば怒り狂い、実力も会員に追い越されて煙たがられているなんてゴシップも飛び出す。とにかくボロクソである。同期デビューした作家の本が平積みになっているのを見ながら、自分の現状を自嘲気味にハカセに語り掛けるシーンなんかは本当に可哀そうになってくる。
そう、今作では明らかに読者が新谷さんに同情するように描かれている。栄光は遠い過去の話となり、現状は全然うまく言ってない。対して親しくもない子供の頼みに親切心を出してみれば、作家としての資質を全否定されるような形で裏切られる。私が小学生の時に読んだ時も、子供ながらに新谷さんに同情していたのははっきりと記憶している。そんな同情すべき新谷さんなので、もちろんその怒りにケリをつけないと物語は収まらない。じゃあそのケリをつけるのが誰かと言うと、もう一人の主要人物である宅和先生である。
明らかに本作のクライマックスは、劇の内容に激昂した新谷さんの自宅に宅和先生が謝罪しにおもむく最終章「教師VS作家」である。ここで二人は酒を飲みながら教育論・児童文学論について喧々諤々とやりあって大喧嘩するのだけれど、これがもうめちゃくちゃ面白い。作者の持つ教育論・児童文学論の興味深さに加えて、いい大人が我を忘れて口喧嘩する様と言うのは見ていて単純に楽しいものがある。詳細はぜひ読んでほしいのだけれど、この喧嘩の中で開陳される、2人の大人(あるいは作者)が抱く子供への「パターナリスティックな甘やかし」とでもいうべき部分が面白かったので深堀したい。
この二人、劇の無断改変という裏切りについて言い争いをするのだが、そこで問題視されるのは徹底して「宅和先生の管理責任」だけである。宅和先生が自分の責任を強調するのはともかくとして、新谷さんが糾弾するのもあくまで宅和先生のみだ。
いいですか、あんたは、三つのあやまりをおかしているんだ。一つは、作者のことわりなしに原作を書きなおした。これは、わたしとあんたの信頼関係をふみにじったということだ。二つめは、教師として、クラスの子どもを指導する立場にありながら、子どものおこなおうとしている劇に、なんら指導をしなかった。そして、三つめ。あんた自身に、文学的教養がまるでないということ。テレビやマンガと文学作品の区別がつかない低級な批評眼しかもちあわせてないということだ。
p298
本文から新谷さんの台詞を引用してみたが、これだけでもちょっとは本作の魅力が伝わるだろうか。とにもかくにも責めているのは徹底して宅和先生のことであり、子供の責任を問う言葉は一切ない。じゃあ彼らは子供たちのやった行為を問題視していないかというとまったくそんなことはない。
「子どものイメージをもつのはいいでしょう。しかし、そのイメージと、現実の子どものギャップに出あったとき、あんたは、たちまち逆上してしまう。今回の劇の台本をたのみにきたのは、うちのクラスの子です。あんたは、あの子の願いをきいて、台本を書いた、つまり、あんたは、現実の子どもを信頼したわけだ。
ところがどっこい、子どもたちは、あんたをうらぎってしまった。あんたは、さっきから、わたしとの信頼関係ばかりいうが、じつはほんとうにうらぎったのは、あなたがつねづね童話でかたりかけようとしている子ども自身なんです。
あんたは、それがわかっているから、だから、腹をたてとるんだ。しかも、うらぎっただけじゃない。あんたの作品をすてて、べつの作品を上演した。そのことが、ショックなんでしょう」
p306
今度は宅和先生の台詞を引用。「子供たちが新谷さんの信頼を裏切った」ことをはっきりと認識していることがわかる。彼らは子供たちに問題があることを知りながら、その責任を一切追求しない「パターナリスティックな甘やかし」を行っている。実際、劇中でハチベエが新谷さんに謝罪しようとしたときは、すでに宅和先生と新谷さんの間で問題のケリがついた後であり、まともな謝罪をする機会すらなく本作は終わってしまう。3人組をはじめとするクラスの面々は、物語上においてなんら裏切りへの報いを受けないし、責任を取らない。
これだけ読むと作者の想定する大人としてのあるべき姿、責任の取り方を書いているだけのように感じてしまうかもしれない。ただ思い出してほしい。本作は児童書であり、主要読者は子供である。子供がしでかした過ちを、子供のあずかり知らぬところで大人たちが争って、子供のあずかり知らぬところで解決する。その様を子供に読ませているわけである。つまり「大人はあなたたちを対等に扱わず甘やかしているよ」というメッセージを子供に見せつけているのに等しい。こういった「子供を一人前に扱っていない」パターナリズムのありかたを児童文学で表現して見せるのは相当にチャレンジングではないだろうか。あるいはこんなに誠実で、子供を甘やかさない姿勢もないのではないか。残念ながら子供のころの私はそこまで深く考えず、宅和先生のヒロイックな活躍ばかりに目が行っていたと思うのだけれど、他の人が子供時代にどんな感想を持っていたのかが実に気になるところである。
余談だが、本作を読んだ後に以下のインタビューをぜひ読んでほしい。大人の本と子どもの本の違いを問われて「セックスシーンを書かなくていい」くらいしか無いという作者の発言に大変な説得力を感じるはずだ。
小山田圭吾(コーネリアス)に対するバッシングと、適度な社会的制裁のラインってなんぞやという話
小山田圭吾氏が、子供時代のいじめを語る過去のインタビューによってバッシングを受けていることに関連して、その社会的制裁が過激化することに対する疑義をちょこちょこ見かける。
自分も適当な社会的制裁ってなんだよーとごちゃごちゃ考えてはいたのだけれども、ちょうど愛読してるブログで同テーマの記事が投稿されていたので読んでみた
上記のデビット・ライス氏の記事についてはおおむね同意するところが多いのだけれども、記事中で引用されてる以下のツイートにひっかかりがあった。
社会的制裁を生み出すような道徳感情は集団や社会の秩序を維持したりするうえでは不可欠なはずであり、社会的制裁が望ましい結果を生み出すこともあるけれど、法律的な制裁と違ってコントロール不可能でありいつ望ましくない結果が出るのかもわからないので、原則的に「社会的制裁はよくない」とすべき https://t.co/xyqyMgRvhh
— デビット・ライス (@RiceDavit) 2021年7月18日
原則的に「社会的制裁はよくない」とすべき、とまで書いているのだけど、さすがにそれはラディカルすぎるんじゃないか?というのがそのひっかかりである。
氏自身も
社会の道徳的進歩というものは多かれ少なかれ社会的制裁によって実現してきたのかもしれないし、それがなければわたしたちは現在よりもずっとひどい社会に住んでいたのかもしれない。
と書いている通り、社会的制裁は必ずしも害のみをもたらすものでは無い。合法な範囲で行われる非倫理的行為に対する対向運動というのは、ほとんどが社会的制裁にならざるを得ないのではないだろうか。
例えば
・大企業が非倫理的な行為を行っている際、それに対する批判や不買運動
・いじめ問題を矮小化しようとする教育機関に対して、批判であったり教育委員会に働きかけることでもってその是正を求めるような行為
・差別的な言動を行う集団や著名人に対して批判することにより、その社会的イメージを減退させようとすること
等々についても社会的制裁と言えるのではないか。印象論になってしまうが、これらの行為がなければ、合法で行われる非倫理的行為は今よりも非常に容易なものとなってしまうだろう。社会的制裁が無くなった社会が今より良い社会であるかと考えると疑問符を抱く。
とはいえ、上記の記事中でもさんざん指摘されている通り、社会的制裁は不適当に・恣意的に・過剰に行われがちでその責任はだれも取らない。結果「過剰に制裁を受けた加害者」「不当な理由で制裁を受けた加害者とされた人」という新たな被害者が容易に誕生するため、これはもちろん良くない事である。いわゆるキャンセルカルチャーへの批判も同型の問題だろう。
というところで、「適説な社会的制裁」というものを仮定したとして、その”適切さ”のラインってなんぞやというのを今回の問題をベースに考えてみる。
今回の炎上の件で言えば、バッシング対象となっているのは以下のポイントだろう。
①小山田圭吾氏が少年時代に行ったいじめ行為そのもの
②インタビュー記事で小山田圭吾氏が過去のいじめ行為を笑い話として語っていること
③そのような記事を載せたライター・雑誌(ロッキンオンジャパン•クイックジャパン)の倫理的責任
また、上記を受けて
④このような非倫理的な行為を行った人物を要職に据えようとした五輪組組織委員会の対応
さらにまとめると、①「いじめ行為そのもの」と②③④「いじめ行為を軽く扱うこと」に対してバッシングが行われていると捉えることができる。
今回のような社会的制裁が特に子供の行う「いじめ行為そのもの」に対する直接的な抑止力になるとはあまり思わないが、「いじめ行為を軽く扱うこと」への社会的リスクは間違いなく上がったと認知されたように思う。
今後、「いじめ行為を軽く扱うこと」が以前と比べて困難になったことは社会的制裁の「良い」点であるだろう。*1
ではこの「いじめ行為を軽く扱うことの困難化」はバッシングが激化する過程のどの時点から発生し、どの時点でバッシングの有用性が失われるのか。
実際のところ、小山田氏のいじめインタビューは10年くらい前に発掘されていて、彼のファン層ではそこそこに有名な話であったし、そこそこには非難されていた。*2
それでもこの10数年間、小山田圭吾氏は順風満帆なキャリアを送ってきたわけで、そこに「いじめ行為を軽く扱うことの困難化」という抑止力は全くと言っていいほど働いていなかったように思う。五輪がらみで炎上したことによって認知者が増えて、初めて社会的制裁は有効に働き、エスカレートして過剰なものとなっていると私は考えている。
まあ、そもそも社会的制裁というのは私刑なので、コンセサスのとれた適当な社会的制裁の程度なんてものは存在しないのだけれど、どの程度が適当かの個人的な基準くらいは定められるかもしれない。
ということで今回のバッシングによって発生した社会的制裁について時期を段階分けしてみると以下のような感じになるだろうか
(1) 問題の存在そのものを初めて周知する行為(例えば10年前ほどにインタビュー記事を発掘した人が行った行為)
(2) (1)を受けてそれを広めたり批判する行為
(3)五輪に伴う炎上でインタビューについて認知し、それを広めたり批判する行為(初期)
-------------------------------この間のどこかで十分な社会的な認知が発生------------------------
(4)五輪に伴う炎上でインタビューについて認知し、それを広めたり批判する行為(後期)
また、上記とは別の軸で
・上記を受けて小山田圭吾氏を五輪の音楽担当から解任する行為
・小山田圭吾氏の過去・未来の活動に対する制限
という社会的制裁もあるだろうが、ここでは触れないでおく。
この段階分けに準じると、(1)-(3)までは倫理的に良い社会的制裁、(4)は過剰であり、倫理的に悪い社会的制裁と言えるかもしれない。じゃあ(3)と(4)の間のラインは具体的にどこなんだよと問われると、正直個人の肌感覚で・・・・以上のことは思いつかないので説得力も何もない整理になってしまうのが正直なところである。
私は現時点のバッシングは(4)の段階だと思っているが、まだ(3)の段階だ!と感じているがゆえに未だにバッシングを続けている人だっているだろう。*3どこかに適当なバッシングの閾値があるのだろうけれども、それを見出すのは相当に困難なことだろうし、そうして見出した閾値がコンセサスを得られるかというのも疑問ではある。このあたりの量の問題については以下の記事がおもしろかった。
現時点でもバッシングを続ける人に対してはあまりいい印象を抱いてないし、私自身この手のバッシングに参加することはあまりないのだけれども、「お前の態度はスマートかもしれないが、他人が泥臭くバッシングしたことによる倫理的向上にフリーライドしてるだけじゃないか」と言われたら反論に窮するところはある。
例えば今回の事例や類似事例に関して、SNSや報道における当該話題の頻出率と公共の場で行われるいじめ問題に関する不適切な発言数なんかの相関を、一連の炎上の前後でとってみたりする、なんて研究があればもう少し説得力のあるラインを引くことができるのかもしれない。とはいっても現時点では机上の空論だし現実味も薄いよなとは思う。
あと、いじめみたいな「明らかに不当であるというコンセサスがとれている」ことならともかく、冒頭のライス氏の記事で紹介されてるスティーブン・ピンカーの例のようなそもそも「バッシングの理由自体が不当である懸念が大いにある」問題については全く別の整理になるよなーとは思います。
「発達系女子とモラハラ男──傷つけ合うふたりの処方箋」の感想と、読んでいて抱いたモヤモヤ
鈴木大介著の「発達系女子とモラハラ男──傷つけ合うふたりの処方箋」を読んだ。別に発達障害の彼女ができたとかそういうわけではなく、単純に鈴木大介ファンだから買った。
この本は前書きで示されている通り、「発達障害特性を持つ女性及び、そうした女性と共に暮らす男性パートナーをターゲットにした1冊」である。そういう意味で自分はターゲットではない。とはいえ、発達障害特性は世間平均よりある気はしている(診断はまず下りないであろうレベルで)のと、そうでなくても発達障害特性を持つ他人との生活におけるライフハック本として一定の普遍性があるようには感じたため、興味深く読めた。
本著は著者(定型発達者)とその配偶者(発達障害者)を例として、各章ごとに
①ある発達障害特性を持つ配偶者はどんな行動が困難か
②発達障害でない著者はそれにどんな不満を抱いていたか(そしてその不満が不当であったか)
③その発達障害特性由来の問題をいかにして解決したか
を解説するという構成を基本的にとっている。まずもって著者の文章は平易で分かりやすく、ところどころユーモラスで読み物として面白い。しかし、それ以上に他のライフハック本と差別化できるポイントは「著者が一時的に発達障害特性をもつ当事者になり、今はそれがかなり改善している」という経歴の持ち主である点である。
著者の鈴木大介氏は数年前に脳梗塞による高次機能障害となっている*1。現在は症状が改善しているものの同一人物の視点から「発達障害特性に対して抱く不満」と「当事者になってみてその不満がいかに不当であったか」を語られるのはやはり説得力がある。
また、特に印象的だったのが「真の公平」とは何かと題して、家事分担について語られている箇所。ここで著者は以下のように記述している。
ようやくたどり着いたのは、妻と僕が家事運営を「平等」に行うことは、ことはなす作業の量や時間を均等にすることでは決してないという理解。そして我が家における公平とは、「脳(認知資源)の消費量で釣り合っている状態」だという気付きだ。
前後の文章も含めて、自分は著者の「結果的な幸福に対するフェアネス」みたいなものを感じた。これは個人的な話になってしまうが、常日頃から無能力な人間に対する苛烈な批判とそれが世間的に肯定されてしまいがちなことに強い不満を抱いている自分にとって、著者のこの姿勢には強い共感とリスペクトを抱いた。
ところどころで定型発達者はその弱者特性を読み取って配慮しなければいけないという規範的なマッチョイズムを感じ、そこに反発するところもあったが、そもそもそのような配慮を行えるようになりたい人間が読むことを想定している文章に対しての批判としては的外れであるだろう。
と、ここまでが全体的な感想。以降は本著のある部分について自分が抱いたモヤモヤについて。これを語るにあたって、まず著者の鈴木大介に対して自分の抱いている勝手な思い入れを書く。
冒頭でも書いたが、自分は鈴木大介ファンであり氏の著書に多大な影響を受けている。著書である「最貧困女子」や「家のない少年たち」で描かれた、「最も貧困である恵まれていない人達は、面倒くさい、かわいくない、加害的な人間であることが多い」という主張は確実に自分の人生観を変えた。
犯罪者であったり、怠惰さゆえに生活を破綻させている人、それを助けようとしている人に対してすら攻撃的にふるまう人たちに対して、そこに至るまでの貧困を調査し、それを考慮せず無邪気に自己責任論を投げかけることへの鈴木氏の憤りはそのまま自分にも刺さった。それゆえに、自分は氏をリスペクトしているし、とても感謝している。彼の問題意識を好ましいものとして考えており、ともすれば過大な思い入れを抱いている。
であるがゆえに、本著8章「発達系女子が働いてくれない」のある部分について耐え難いモヤモヤを感じてしまった。
8章は以下のような構成になっている
①著者が働かない配偶者に対して、公平感がないと不満を抱いていたこと
②著者の配偶者が現代社会で労働することの困難性の考察。そして本当に不満だったのは公平感のなさだけでなく、配偶者がなんの役割も持っていないと感じていたこと。
③著者がジェンダーロールに縛られていたがゆえに、配偶者の果たしていた役割に気づいていなかったこと。それに気づいて不満が解消されたこと
上記②⇒③への論旨が自分がモヤモヤを抱いたポイントとなる。
ここで筆者は「外で働くという役割を持たない妻は、家事労働をするか育児をするか何らかの役割のもとに生きるべき」という規範を持っていたことを反省する。その理由として、この発想を突き詰めると役割のない、生産性のない人間は存在すべきでないという思想に接続され、それは相模原障害者施設殺傷事件の植松聖の論を正当化に与するものとなる、と語る。そして、配偶者がいることにより「仕事後に独りで食事をせずに済み、気持ちが削られたときにそれを共有してもらい、答えの出ない悩みを抱えた時に今を楽しむ提案をしてもらえた」ことに気づき、「誰かのパートナーが務まる」ということだけで得難い役割を果たしてくれていると結ぶ。
筆者がその配偶者のあり方を肯定できるようになったというのは単純に祝福されることであるとは思う。しかし、それに至った理由として書かれているのは「役割を担っていないと感じていた妻が実は重要な役割を担ってくれていたことに気づいた」である。では、本当に役割をもてない人、他人に対して魅力のある何かを提供できない人はどうなるんだ?というのが自分の抱いたモヤモヤだ。
人は何のメリットも提供できない相手と婚姻しない、ゆえに言及する意味がないというのが正しいかもしれない。正直ここにケチをつけるのは不当な気もしているのだけれど、それでも「何も持たない人たち」の困難さや悲惨さを取材し、彼ら彼女らが不可視化されることに憤ってきた鈴木さんにだけは言及してほしかった。そして、それについて語らないのであれば、なぜ植松に触れたのか。実は配偶者には気づいていない役割があった、では植松の論に対する反論にはなっていない。なら言及すらしないのが誠実なんじゃないのか。
あるいは、それについて語ったところで建設的なことを何も言えなかったからなのかもしれない。「何も持たない人たち」をどうやったら救えるのかがわからないという氏の絶望は過去の著書から伝わってきた。何も言えないなりに植松に触れることによって読者に「何ももたない人」について考えさせようとしたのかもしれない。 それでも、氏はこれまでに「何も持たない人たち」を何とかしようともがいてきた人であるとも思う。たとえば「家のない子供たち」や「ギャングース」で、筆者は”最貧困男子”達の犯罪行為をヒロイックに描いてきた。それは加害者になりがちであるがゆえに、女性以上に同情されにくい最貧困男子に対する世間の目を変えようとする試みでもあったと思う。自分は情動でもって他人を説得しようとすることに対して反発を抱くことが多いが、それでも氏のそれが不誠実だとは思わなかったし、むしろ尊敬すらしていた。そんな氏にだけは真正面からこの問題に触れてほしかった。
ここまで自分の抱いたモヤモヤについて書いたが、ある問題についていかなる場所でも言及しろという態度は正統とは言えないだろうし、問題の重さを考えるとそこに向き合い続けろと言うのはあまりにも酷なことであるだろう。なによりこの本のメインはライフハックの紹介であって、枝葉となる話題に厳密性を求めるのもどうなの?という気もする。つらつらと書いたは良いものの、自分が著者に対して抱く身勝手な思い入れからの不当な非難に過ぎないのではとも思っている。
--------------------ここから追記(4/4)---------------------------------
ありがたいことに鈴木大介氏から本記事への反応をいただいたので載せておく。
こんなにも深く読んでくださる読者がいらっしゃることに鈴木は心底感激です。
— 💲鈴木大介・文筆業💲 新刊『発達系女子とモラハラ男・傷つけあうふたりの処方箋』(晶文社) (@Dyskens) 2021年4月3日
ご指摘部分、校了後の朝に「あ、あそこはもう一言加筆が必要だったのでは」「さすがに気づく読者はいないかな」と思った部分なのです!
赤面、後悔、でも著者とここまでシンクロしてくれている読者がいる、この著者冥利。
「〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチ」が面白かった話と、それにまつわる個人的なこと
ウィリアム・マッカスキル著の「〈効果的な利他主義〉宣言! ――慈善活動への科学的アプローチ」がめちゃめちゃ面白かったので簡単な紹介を。あと最近の自分の行動について色々考えさせられたのでそれも。
本著は「効果的な利他主義」という考え方についての紹介本である。ものすごくざっくり説明すると、「世界をよりよくしようと慈善活動なんかをやるなら、より大きい効果のある活動をしよう。そのためには証拠を元にした合理的な活動が必要である」というもの。基本的には功利主義的な考え方がベースだと思う。以下のサイトに概要が乗ってたので詳しくはそっちを見るといいかも。
本著の冒頭では、効果的で”ない”利他主義の例として、「プレイポンプ」が紹介されている。
プレイポンプとはメリーゴーランド型の水くみポンプで、子供たちがプレイポンプをぐるぐる回して遊ぶことで水がくみ上げられるという発明である。それまで重労働だった水くみからアフリカの女性たちを解放し、そのうえ子供たちに遊具を提供できる、といった一挙両得の代物だ。この発明は2000年代の当時、国際的に高い評価を受けて多額の融資を得ることに成功した。
ところが現実に配備されたプレイポンプは、効果的どころかむしろ有害とさえ言える結果をもたらした。通常の遊具と違って回すのに一定の力を必要とし続けるプレイポンプは遊具としてほとんど使われず、ほとんどの場合は従来通り女性たちがメリーゴーランドを回す羽目になった。その上プレイポンプのくみ上げ効率は元々使用されていた水くみポンプと比べて悪く、結果的に現地民の負担を増やしただけという惨憺たる有様であった。
一方で、効果的な利他主義の例として、マイケル・クレマーによるケニアの子供たちへの教育支援活動が紹介されている。彼は現地の14校を7校の2つのグループに分けて、どのような支援が就学率やテストスコアの改善につながるかのランダム化比較試験を実施した。ある支援を7校に実施して、一方の7校を普段のままにしておけばどんな支援が効果的かわかるというわけである。その結果は驚くべきもので、「教科書の支給」や「教員の増加」などの当初有効だろうと想定されていた試みにはほとんど効果がなく、「特許切れの薬を用いた腸内寄生虫の駆虫」が圧倒的に高いコストパフォーマンスを誇る方法であったというものだった。駆虫プログラムは学校への出席率を上げるだけでなく、子供たちへの健康面・経済面にも多大なメリットをもたらしたことが追跡調査で判明している。
プレイポンプは効果的どころか有害な影響をもたらしてしまったが、プレイポンプの発明者や支援者たちに悪意があったわけではない。善意の利他的な活動も場当たり的にやっては有害になりうるわけで、効果的な活動をしたいのであればクレマー達のような科学的なアプローチによる「効果的な利他主義」を行うべきだ、というのが作者の主張である。
この本は2パート構成となっており「効果的な利他主義にとって重要な5つの疑問」として効果的利他主義の考え方を解説するパートⅠ、「効果的な利他主義を実践する」として効果的利他主義を実践する上で具体的に何をすればいいのか?について記載するパート2に分かれている。
パートⅠでは利他行動を定量的に評価するための指標や手法について記載されている。個人的に面白かったのが以下の内容。
・行動の評価は「この行動を取らなければどうなったか」との比較によってきまる
・成功の確率が低いが成功時の見返りが大きい行動もあり、定量的に評価するにはその行動の「期待値」について考える必要がある
特に後者についてはよくネット上で話題になってる「選挙に行く意味はあるのか?」という投票行動の効果について考察していて面白かった。本書では個人の投票が選挙に影響を与える可能性はものすごく低いが、影響を与えることができた際のリターンは大きいため時間単位の利益に換算すると中々効果的かもしれない(数千ドルの価値があるかもしれない)という議論が展開されている。ただし本書内でも触れられているが、この数値は「どの政党に投票すべきかが完全にわかっている人間の投票である」「優れた政党に投票した際の個人の利益が完全に架空の数値(1000ドル)であり、全体の利益もそれに全人口をかけただけの数値である」などと様々な前提がある上での値であってかなり怪しいのが残念。
特にほとんどの人間が持つ情報量や思考力を考えると「どの政党に投票すべきか」を把握できている人間なんて自分含めてほとんどおらず、多分に党派性や雰囲気に左右された投票をしているだろうと思うのであまり現実的でない議論ではあるなと感じた。
パートⅡでは「具体的にどの慈善団体に寄付するのが効果的か?」「どんな製品を買うべきか?」「どんな職業に就くべきか?」といった具体的な行動について記載されている。個人的に面白かったのが以下の内容。
・発展途上国の労働者にとって搾取的であったりエコでない企業の商品をボイコットすることが多くの場合功利的でないということ
・利他的なキャリア形成の話(より利他的な職業に就くか、収入の多い職業について寄付をするかなど)
特に面白かったのは前者の議論の中の、「温室効果ガスの排出を抑えた製品を買ったり日常で電気製品を節約したりするより、安い製品を買って別の温室効果ガスを削減する活動に寄付したほうが効果的である」といった主張。少額の寄付をするほうがライフスタイルを大幅に変えるより楽だろうというのは間違いないので、現実的な対処方法として興味深かった。
温室効果ガスについてはヴィーガニズムの主張でよく採用される「肉食は環境負荷が高い」という主張へのカウンターとしても働くので、あくまで動物福祉に着目すべきではという議論も展開されている。ここで作者は「自分自身が肉食を絶つのでなく、動物愛護団体に寄付してヴィーガンを増やすことで自分自身が肉を食べたことを相殺できるのでは?」という疑問を「苦しむ動物が入れ替わるだけであり、浮気をしてそれを相殺するようなものである。だれもが倫理的でないと考えるだろう」と一蹴している。これについてはトロッコ問題などでよく話題になる「5人を救うために1人を犠牲にすることは許されるか?」という問題にも通じるし、功利主義的に自明のこととして簡単に流せる問題なのか?という疑念を持った。例えば1人の人間を殺して臓器提供することで5人の人間の命を救えるという話であれば、「自発的でない形で自分の命が5人のために犠牲になるようなリスクをはらむ社会で我々は過ごしたくないから、現実社会においては功利的でない」というような反論があるかもしれないが、人間以外の動物ではこの理屈はあてはまらないだろうし。
全体として功利主義にある程度親しんでいる人であれば、素直に受け止められるような内容であり、「現実の行動に落とし込む」という観点で非常に役立つ本であるという感想。ただし、例えば「ヴィーガン的なライフスタイルは肉食をするよりも倫理的である」みたいなのが自明のこととして展開されるのは日本だと忌避感を持つ人が多いだろうなとは感じた。とはいえ細かい議論に異議があったとしても、慈善活動に興味がある人は読んで損はしないんじゃないでしょうか。自分もヴィーガンではないけど去年で一番面白かった本です。
ここからは個人的な話。
ちょうどこの本を読む前に日本ユニセフのマンスリーサポートプログラムで寄付を始めていた。それと昔から国境なき医師団への毎月の寄付をしている。実はこの本ではユニセフ(もちろん日本ユニセフではないけれど)にも触れられていて、「ユニセフのような大規模な団体はやってることの範囲が広く評価が難しい。その中ではあまり効果的でないものも含まれているであろうから、そこへの寄付は最も効果的な支援とはいいがたい」といった旨が書かれている。
これは確かに「効果的な利他主義」的にはそうなるだろうなという結論だ。ただ、自分がはそこまでストイックに慈善活動をしていない。基本的には「自分は善人である」という自己肯定感を担保したいがためにやっている部分が大きく、なるべく慈善活動によって生活負担をかけたくないというのが本音だ。本著でも最も効果的な寄付は「その活動が現在効果的である」「寄付を有効活用する資金の余地がある」必要がある点について述べている。例えば過去に非常に効果的だった「天然痘の根絶活動」に対する支援は根絶が実現された今となっては意味がない。ストイックに効果的な利他主義を実践するなら「その活動への寄付が現在も効果的か?」という継続的な監視が必須であり、それは大変めんどくさいのであまりやりたくない。となると、手広い活動をやっていて実績があるため、「最も効果的ではないがそこそこ効果的な活動」を長期間やってくれるであろう大規模な慈善団体への毎月の寄付は合理的であるかなという自己正当化ロジックを思いついた。あと、一度始めた寄付をやめるのは気が引けるとか、手続きが面倒くさいみたいなのもあるのでとりあえず放置しようと思っている。
活動という意味だと、ここ数年は帰省しなかった年末年始のみ支援団体の主催するホームレスへの炊き出し&夜間パトロールのボランティアに参加している。これについては、前々から自分が参加することによる利益はほとんどないだろうなと感じていた。
炊き出しについては作業分担を仕切ったり実際に炊事を行ったりするのはスタッフであったり年間を通して継続的に活動しているボランティアである。自分のような年末年始だけ参加するようなボランティアは単純作業(野菜や肉の切りこみなど)をやるわけだが、例年20人いればできるような作業を80人が取り合いながらやっているような状況に感じている。夜間パトロールについてもコアメンバー以外はほとんど「見学をしにいっている」だけの状態である。
少なくとも炊き出しについては量が多いため一定の頭数が必要であり、余っているぐらいでないと主催側としても不安要素となるだろうし、作業負担の分散という意味では効果があるのだろうとは思う。しかし夜間パトロールについては労働力としてのボランティア参加はほとんど求められていないだろうと感じていた。実際に活動の代表者の方がボランティアに向けて話す内容は、ほとんどが「現状を知って考えてほしい」というものであった。ボランティアに対して労働力としての期待はほとんどなく、啓蒙的な理由がほとんどをしめているのだろう。あるいは後々コアメンバーになってほしい、という期待もあるのかもしれない。
以上を元に考えると、継続的な活動を続けるバイタリティは完全になく、かつそこそこの回数を参加している自分が単発的なボランティアとして参加する意義はほとんどないだろう。下手をすると新規のボランティアが啓蒙される機会を奪っているだけのようにも思う。とはいえ総合してマイナスにはならんだろ、というのと自己満足はできるだろう、という気持ちで例年参加していた。今年はコロナでボランティア足りないのでは?という懸念があって12/30~31で参加したものの、幸いなことに余るぐらいのボランティアが参加していた。今年については自分の参加はコロナリスクを上げるだけだなとも思ったので、それ以上参加はしていない。
あとは、この炊き出し&パトロール自体が「効果的な利他主義」からは程遠いものではあるのだろう。そもそも「効果的な利他主義」の理屈で言うと先進国で国内向けにやる支援はほぼすべて「効果的でない」という結論になってしまうのだけど。*1
コアメンバーの方から「炊き出しに来ている人もほとんどがホームレスでなく近隣のドヤに住む生活保護者であり、浮いた金をギャンブルに使っている。不毛に思うことも正直あるが、わずかなホームレスのためだけを思ってやっている」みたいな話も聞いた。実際炊き出しに来ていた人の顔を近くのボートレース発券場の行列で見たことは何度もあり、説得力を感じた話ではあった。とはいえ、わずかなホームレスへの支援だって好ましい活動ではあるし、「あなたを気にかけているということを伝えたい」という理念は素晴らしいものだと思うので、活動自体は応援している。ホームレス以外の生活困窮者が炊き出しを食べに来て、それで浮いた金を娯楽にあてるのも悪いことだとは思わない。(ギャンブル、となると無条件で肯定はできない気持ちもあるけれど)「最も効果的」でない活動はするべきでない、という考えはそれはそれで有害だろう。
ちなみにこの年末年始のボランティアに政治家の山本太郎が参加しているのがちょくちょく報じられているのを見かける。実際、毎年どこか1日はほかのボランティアに交じって切り出しなり配食なりを手伝ったり、寄付金を渡したりしている光景を見かけた。自分は氏を政治家としては最悪の部類だと考えており人間的にも嫌っているのだけれども、こういった活動を継続的にやっているのは素直にリスペクトしている。福祉の現場に直接参加しない政治家はダメ、みたいな言説は心底馬鹿にしているけれど、それはそれとして直接参加することは悪いことじゃないだろう。*2あと、自分は本当に山本太郎が嫌いなので、せめて山本太郎より貢献してやろうと考えて風のうわさで聞いた山本太郎の寄付額の数倍を寄付したりしたこともあったので、著名人の慈善活動ってそこそこ効果あるんだろうなーと思ってます。
以下参考サイト
効果的利他主義への批判記事。中身はまだ読んでない。
本著の読書目メモ。自分はこれを読んで購入した
好意的な書評
ピーター・シンガーが効果的利他主義について語るTED。まだ見てない
名字の収束した世界で佐藤と鈴木は争うんだろうか
現在の日本の法律だと婚姻するなら双方の名字は同じにしないといけないわけだけれども、世の中には人口の多い姓ってのがあるわけで、このまま世界が続けていけば必然的にマイナーな名字は淘汰されて行く。現在メジャーな名字だけが残っていくわけだ。
ようするに日本は佐藤や鈴木、高橋や田中のみに牛耳られていく。たぶん人口比の90%が4つの姓とかに収束した世界は個体識別に名字が使えなくなるので、現在主流な2~4文字くらいの名じゃ同姓同名が多すぎて厳しくなってくる。そうなると名前がどんどん長くなっていくか、古式ゆかしい方法、すなわち地名や関係性、容姿や職業に絡めた名乗りが主流になってくるかもしれない。
「アキヒコとヨシエの息子、湘南の佐藤太郎」とか「襟裳岬のエンジニア、赤毛の鈴木花子」みたいなやつが実用されるかもしれない。それはとても素晴らしい世界だと思いませんか。いや、思わないけど想像するだけどにこやかな気持ちにはなってしまうし、とにかくそんな世界を見てみたいというこの気持ちだけは本物であると確信している。
そんな名字が同じ人間が周囲に溢れている環境で、人は何を考えるんだろう。名字、というか、名前と自分のアイデンティティを強く結びつけて考える人間は多いだろうけど、全体の30%とか40%が同じ苗字の環境下で名字に個人としてのアイデンティティを感じるのはだいぶ難しくなる気がする。ただ、その代わりに集団としての帰属意識は生まれないだろうか。国籍や人種、性別のように、名字に対する帰属意識が生まれてもおかしくないんじゃないか。
大体の人は何でも間でも関連付けるのが好きである。それが何であり、特定の「何か」の区分けによって集団が存在し、そこにアイデンティティを感じるものがいるとすれば間違いなくその「何か」に付帯して別の「何か」がどんどん関連付けられていく。「田中」姓は名字が田中であるという事実にのみ定義づけられるものではあるが、そこに「田中」は○○の傾向があるといった言説が出てくるのは想像に難くない。今だって姓名判断なんてものがあるくらいである。「鈴木」は社交的・活動的であるが慎重さに欠けるとか「佐藤」は誠実で頭が良いが受け身がちであるとか、そういう話が好きな人はたくさんいる。そこに確固たる根拠は必要ない。著名な「高橋」姓のスポーツ選手が多ければ「田中」は運動能力に優れていることにされるだろうし、「佐藤」姓の学者や医者が多ければ「佐藤」は頭が良いことになる。サンプル数の少ない精度の低い統計でもセットにしてあげればそれを振り回す人は大勢いるし、思想や能力と名字に因果関係があると信じる人が少なからず現れるだろう。相関と因果を逐一判断するのはなんやかんや難しい。
アイデンティティを感じているものに対して、自分のそれが優れていると結論付けたがるのはまあよくある話である。佐藤太郎は「佐藤」が鈴木より優れていると考える。鈴木花子は自らの「鈴木”性”」を誇るはずだ。そこに待つのはお決まりの争いだ。レッテルの張り合い、統計のチェリーピッキング、程度の低い対向論だけを取り上げて一般化する、その他もろもろ。
ここまで考えて思い出したのがカート・ヴォネガットの『スラップスティック : または、もう孤独じゃない!』だ。
自分が一番好きな小説のひとつであるのだけれど、この本の中に「拡大家族」計画というのが出てくる。政府が国民に新しいミドルネームを発行する。ミドルネームが同じ人達はみんな親戚だよって計画だ。例えば佐藤太郎さんと鈴木花子さんには縁もゆかりもない。そこで政府が2人に「梅干し」というミドルネームを勝手に発行したとする。佐藤・梅干し・太郎と鈴木・梅干し・花子はたちまち親類縁者だ。縁もゆかりも発生するわけでそうやって孤独を無くそうというのがこの計画の趣旨である。もちろんこの作品はフィクションであるけれども、思考実験としては面白い発想だと思う。職業でも趣味でも、共通点があれば人は親しみを抱きやすいというのは事実だ。政府が「勝手に」付けるので、だれを身内にするかは誰も選べない。蛇蝎のごとく嫌っている相手だろうと勝手に家族になってしまうわけなので、当人の資質によらず孤独から逃れられてしまうというわけである。
作中でこの拡大家族計画がうまくいったのかはよくわからない。ミドルネームによって派閥を作ったり、性向について語られたり(ピーナッツ家は卑しい!)、そこそこに孤独が解消されていたりする描写はある。だが拡大家族計画が実施されてまもなく、「緑死病」という謎の疫病のパンデミックによってほとんどの人間が死に絶えてしまうので、政策もなにもあったものでは無くなってしまうからである。ちなみにこの緑死病、作中では中国発の疫病だったりするので、めちゃめちゃタイムリーな話でもある。というか、コロナと絡めてこの本の話する人がいっぱい出てくると思ってたのに、そうでもなかった悲しみを昇華すべく書いたのがこの記事である。「ここまで考えて思い出した」なんて書いたがあれは嘘ですごめんなさい。スラップスティックはヴォネガット作品の中だとかなり感傷的というか、「猫のゆりかご」とか「ローズウォーターさん、あなたに神のお恵みを」なんかの突き放した残酷さみたいなのが薄くて読みやすいと思うのでぜひ読んでね。
「拡大家族」についてはヴォネガット自身思い入れのある考えだったらしいので、作中で描かれる拡大家族は中々捨てたもんじゃないように見えるのだけど、実際のところどうなんだろう。現代日本での婚姻制度がこのまま続き、名字が収束した世界はスラップスティックの世界と近似している。田中が田中同士で連帯する光景はもちろんあるだろうけれど、田中は高橋を嫌悪し迫害しないだろうか。佐藤と鈴木は争うんだろうか。そういうことを考えている。ぶっちゃけ血液型診断のB型差別程度で収まる気もする。それが良いことであるかは別にしてめちゃくちゃ見てみたい世界であるので、夫婦別姓への反対意見に賛同する気持ちが全くないとは言えない。
いやまあ、夫婦別姓が可能なほうが便利ではあるし、究極的には既存の婚姻制度自体が解体されるべきじゃないの?という考えなので夫婦別姓になったらいいとは思う。以下の記事とほぼ同一意見です。
※追記
冷静になって考えると夫婦別姓になろうが創姓できない限り名字は収束していくので、将来的に佐藤と鈴木の合戦が起こるのは既定路線ということでお願いします。
これからの世界をより良いものにするため、私たちはご飯に箸を突き立てなければならない
実家では箸置きというものを使う習慣がなかった。確か4,5歳くらいの時だったと思うのだけれども、夕食の時間に箸の置き場所に困った自分は、茶碗に盛られたご飯に箸を突き立てた。ごはんの粘性は相当なもので箸はぴたりと静止してくれた。これならテーブルを汚すこともない、何て自分は冴えているんだと当時思ってたかは記憶にないが、それを見た母親は「箸を刺したご飯は死者への食事という意味を持つのでやめるべきだ」と言って俺のことを注意した。その言葉に強い反感を抱いて、「母さんは死者が食事をすると信じているのか」「死者への食事という意味を持つからといって、自分がそれをやめなければいけない理由はあるのか」といったような反論、というか質問を投げかけたように記憶している。それに対しての母の回答は「私は信じていないが信じている人はたくさんいる。そういった人が見ると不快になる」「宗教的な意図に関係なくとも、単純にみっともない」といった内容だった。幼少期の自分は親にとても従順であったため、釈然としないながらも引き下がった。
年を重ねるにつれて「宗教的な儀礼を除いて箸をご飯に突き立てるべきでない」という規範は自分自身にも深く根付いていった。思春期に差し掛かかるころには「日常の中でご飯に箸が突き立てられている光景」を見て直感的に不快感を抱く程度には。
さらに長じて倫理とか規範とかに興味を抱き始めてから、幼少期のこの出来事に対して強い反発を覚えた。幼少期の自分に対して母親が示したルールは、要するに以下2つのような意味合いとなると考える。
「私は信じていないが信じている人はたくさんいる。そういった人が見ると不快になる」より
①自分が尊重していなくとも、他社が尊重している信仰や規範(平時にご飯に箸を突き立てるべきでない)は、自分の便益(机を汚さない)を害しても配慮すべきである
「宗教的な意図に関係なくとも、単純にみっともない」
→箸を突き立てられたご飯に対して「みっともない」と感じるのは明らかに生得的ではないと考える。実際のところ後天的に植え付けられた規範からの逸脱に対して不快になっていると考えると、*1
②すでに共有されている規範・マナーから逸脱すると人は不快に思うため、規範・マナーから逸脱すべきでない
ちょっと露悪的に書きすぎたきらいはあるけれど、この2つのルールって本当に正しいか。
①「自分が尊重していなくとも、他社が尊重している信仰や規範は、自分の便益を害しても配慮すべきである」について
当たり前であるが、個々人によって尊重している信仰や規範は違う。ただ、共通してる部分もかなり多く、例えば現代日本人の多くは自由や平等だったり人権思想に基づく価値観(以下、世俗倫理と表記)について、強く尊重すべきものであると考えている。信仰していると言い換えてもよい。一方で特定宗教の人格神みたいなものは信じていないし、その教義の基づく規範(以下、宗教倫理と表記)に価値を見出さない。見出さないは言い過ぎにしても、少なくとも自由や平等などの世俗倫理がより優越すると考えている。自分は平均よりかなりラディカルだと思うけれど、同様に世俗倫理を支持し、宗教倫理より優越すると考える立場にある。
具体的な例を考えてみる。例えば原理主義的なキリスト教徒が「同性愛者は倫理的に悪であるため社会から排除すべきである」と主張しても自分はそれを尊重しないしその思想に基づく実力行使を許容しない。なぜなら「同性愛者は倫理的に悪であるとする聖書の記載」に自分は価値を見出さない。「原理主義的なキリスト教徒が同性愛に対して抱く不快感情」については価値を見出すが、「同性愛者の幸福追求権や自由権」がそれに優越すると考える。なぜなら自分は世俗道徳を尊重し支持しているからである。宗教倫理と世俗倫理が背反するときには世俗倫理が優越されるべきで、それは世論だったり、それに実行力を与える法律や暴力装置によって施行されるべきと考える。*2
ここまでの整理については大多数の人に同意してもらえると思う。「宗教規範」と「世俗規範」が対立して共存できない問題については、他社の尊重する「宗教規範」を踏みにじってでも自分が尊重する「世俗規範」の基づいて社会が運営されるべきと考える。どれだけ他者の価値観を尊重するとは言っても、共存できないものはある。そうなったら、その社会で尊重される規範は身も蓋もないパワーゲーム*3で決定されるしかない。これについてはISISの騒ぎで個人的に痛感したのだけれど、実際問題として世俗倫理に反する宗教倫理を現代で志向しようとすると暴力に頼るほかないし、それに対するカウンターだって経済的・暴力的なパワーゲームで押しつぶすしかない。人権思想よりコーランの字義通りの解釈を尊重している相手に「お前は人権思想に反している!」と言っても対立者に対してはまるで効力がない。*4
さて、話を戻してこの理屈が「ご飯に箸を突き立てること」にどのように適用されるかを考える。ここで対立するのは「ご飯に箸を突きたてることで便益を得る」自分の自由権・幸福追求権と、「ご飯に箸を突き立てるべきでない」という宗教倫理である。これは共存し得ないので、世俗倫理を尊重する立場からすると「ご飯に箸を突きたてることで便益を得る」ことが優越すべきであると考える。不快になる人間に配慮して箸をご飯に突き立てないことは賞賛すべきかもしれないが、配慮をしないことについて非難されるいわれはないと考える。私はシャルリーを引き合いに出してもいいけれど、他者の規範の尊重は、私の尊重する規範を害さない範囲でないともちろん認められない。人権思想や表現の自由は自分にとって宗教倫理より優越する。宗教倫理を害す表現に対しての批判、「ムハンマドの顔を書くべきでないし、揶揄すべきでない」という主張は許容できても、ムハンマドの顔を書き揶揄することは制限すべきでないし、それに対する実力行使は許容できない。なぜなら自分は「ムハンマドの表象を書くべきでない」という宗教倫理より表現の自由という世俗倫理をより尊重する立場にあるからである。
まあ、そもそもこの「ご飯に箸を突き立てる」ことに対して特別な意味合いを見出してる教義って明確にはないみたいで、「仏教・神道の教えっぽいとみんなが認知してる慣習」以上のものでは無いっぽいので、宗教倫理とするよりも単純なマナーの問題と考えたほうが筋は良いと思ってます。ということで次の話につながります。
②「すでに共有されている規範・マナーから逸脱すると人は不快に思うため、既存の規範・マナーから逸脱すべきでない」について
これを言い換えると
①マナーを破ると人は不快に思う。
②人を不快にする行為は好ましくない
③上記より、マナーを破る行為は人を不快にするため好ましくない
いやー完璧な3段論法が完成してしまった。ただよく考えると「マナーはそれがマナーであるから守るべきである」と言っているのと何ら変わりない発言である。そしてこの「マナーはそれがマナーであるから守るべきである」という考えについて自分はそれはそれはもう憎悪を抱いている。
まず、ここでいう「マナー」という言葉について自分は「緩い規範」くらいに定義している。例えば「人を殺すべきでない」みたいな基本的に絶対に逸脱すべきでないし、逸脱したら重大なペナルティと非難が避けられない「重い規範」とは対照的に、「逸脱するのはなるべくやめたほうが良い」くらいの「緩い規範」=マナーということで話を進める。
何かのマナーに価値があるとすると、そのマナーを守ることによってメリットがある場合であると考える。なぜならマナーとは往々にして「○○をすべきである」「○○をすべきでない」とい行動の強制を伴う規範であり、選択肢を狭めるものであるからである。基本的に選択肢は多いほうがいいと自分は考える。
さて、例えば「電車の乗り降りは降りる人を優先すべき」というマナー。このマナーが広く共有されていることにより、電車の乗り降りをスムーズに行うできる。確かにこのマナーを守ることによってメリットが存在するため、「電車の乗り降りは降りる人を優先すべき」というマナーには存在価値があるだろう。
ひるがえって「ご飯に箸を突き立ててはいけない」というマナーに価値があるだろうか。真っ先に思いつくのが「ご飯に箸を突き立てている光景を見ることによる不快感」を回避できるというメリットだ。たださらに思考をすすめてなぜ不快に思うのか?を考えると「ご飯に箸を突き立てるのがマナー違反であるから」に行きつくだろう。「ご飯に箸を突き立てること」に対して特別な意味を見出しているのは日本だけのようだし、ご飯に箸を突き刺して悦に浸っていた幼少期の自分を例にとってみても、この不快感は生得的なものとは思えない。*5多くの人は後天的に「ご飯に箸を突き立てることはマナー違反である」と学習し、そのマナーが逸脱されたことに不快感を抱いていると考えられる。つまり、「ご飯に箸を突き立ててはいけない」からこそそれに不快感を抱く人がいるのであり、そもそもこんなマナーが存在しなければ多くの人は箸にご飯を突き立てられている光景をみてもおそらく何とも思わない。
マナーが増えるということはもちろんマナー違反が増えるということでもある。つまり、マナーが増えるとマナー違反による不快を感じる機会が増えるとも言える。これは本当に声を大にして言いたいことで、「それがマナーであるから」以外に守る意味のないマナーは不快を感じる機会を増やしているだけである。不快を感じる機会は減らしたほうがもちろん良いので、メリットのないマナーなんて無いほうがいい。ご飯に箸を突き立てて机を汚さないメリットを自由に享受できる社会のほうが絶対にいい。自分がマナー業界を蛇蝎のごとく嫌っているのはこの辺が理由で、メリットのないマナーを創作して稼いでるあいつらマジで不幸の商人だよ・・・・・と思っている。
と、ここまで書いたけれども、実際のところ「それがマナーであるから」以外に守る意味のないマナーにもメリットはある。マナーに合理的な意味があろうがなかろうが、「その場において支配的な規範=マナーに従順でない」人間、長いものに巻かれない・巻かれることのできない人間を排除する上では非常に有効に機能する。良く言えば自立した人間であり、悪く言えば協調性のない人間だ。こういう用途で使うならむしろ合理的なメリットなんて存在しないマナーの方が有用かもしれない。とはいえ、自分の信仰としてこういった排除のロジックは気に食わないのでやっぱり「それがマナーであるから」以外に守る意味のないマナーなんて無いほうが良いと思う。マナー業界はいち早く滅びてほしい。
ここまで読んでくれた方なら、我々はご飯に箸を突き立てるべきであると十分に理解していただけたと思う。実際問題として「平時にご飯に箸を立ててはいけない」というマナーは多くの日本人に強烈に内面化されており、箸が突き刺されたご飯を見ると理屈に関わらず一定の不快感を生じてしまう。これは自分だってそうである。ご飯に箸を突き立てる人は、間違いなく突き立てなかった時より嫌われる。それでも、嫌われるから、すでに定着してるからなんて理由で有害なマナーを継承していいのか。それがなんであり、どのような影響を与えるかについて何の疑問も抱かず、ただ「私はマナーを守っているから道徳的である」と悦に浸っているだけでよいのか。それは将来の不幸を増やしているだけじゃないか、そんなものに迎合していいのか。他人に自我を預けていいのか、自分を誇れるのか。
「ご飯に箸を突き立てるなんてマナー違反だ」という前に少し考えてほしい。なぜ?と聞かれたときに十分な説明ができるだろうか。誇りをもった説明ができるだろうか。実際、子供にそれを言わないのは難しいだろう。ご飯に箸を突き立てる子供は間違いなく悪意にさらされるし、それをはねのけろというのはあまりにも酷だ。でも、それがただの処世術だと伝えることはできるはずだ。幼児には無理でも、中学生、高校生ともなればこの理屈は理解できる人が多いはずだ。せめて、突き立てられたご飯を許容することはできるはずだ。社会は時に非合理で非倫理的になるが、あなた自身までそうなる必要はない。非道を止められなくとも、一緒になって非道をやる理由はないはずだ。ベストを選択できないことはベターを選択しない理由にはならないはずだ。
将来のことを考えてほしい。より良い世界のことを考えてほしい。私たちはご飯に刺さった箸を見たら不快になる。箸置きがなければ直接箸を置くしかないし、机の上はご飯粒でぐちゃぐちゃだ。まかり間違ってもご飯に箸を突き刺さないように気を付ける食卓はピリピリして緊張感に溢れている。それでも私たちがここで勇気を出してご飯に箸を突き立てれば、他人から嫌われることを厭わず「そんなマナーは無いほうが良い」と言い続ければ、そんな人が増えていけば、次の世代ではどうだろうか。「ご飯に箸を突き立てるべきでない」なんてマナーの存在を知らない世代の食卓はどんな光景だろうか。
彼ら、彼女らは箸置きがなければご飯に箸を突き立てることができる。箸置きが無くったって机は清潔に保たれるし、それを見て不快に思う人なんかいない。ご飯に箸が突き刺さっていたからそれが何だというのだ?机にへばりついた米粒なんて誰だって片付けたくはないではないか。ご飯に箸が突き立つ、そんな清潔でリラックスした食卓は朗らかな幸福に包まれている。それはささやかながら、今よりももっと良い世界であるはずだ。
これからの世界がそんな素晴らしいものであってほしいなら、これからの世界をより良いものにするため、私たちはご飯に箸を突き立てなければならない。
ISIŞとイスラム教と動物倫理とヴィーガンと規範を内面化することについて
ISISとイスラム教と移民と
自分がここ10年ほどで最も衝撃を受け、興味を惹かれたニュースはISIS(イスラム国)の出現だったと思う。
自分や自分の所属する社会が共有している道徳や規範(それは平等主義だったり人権思想だったり民主主義だったり自由主義だったり)とはまったく違う規範を持った集団がいて、暴力をもって自分達の規範に挑戦して来ているということが強烈だった。一時期は自分にしては随分と熱心にニュースやそれに対する反応を追っていたと思う。
そんな中で、ISISに対する反応の一部に強烈な違和感を感じていた。「彼らは本当のイスラム教徒ではない。キリスト教徒や仏教徒のように我々と共存できる良き隣人だ」みたいな内容だ。まあちょっと考えただけでバカな発言ではある。一般的な日本人の常識レベルの知識でも、キリスト教や仏教の教えの中に今の私たちの価値観から見ると到底容認できないような差別的な主張や表現があることは知っている。それを字義通り受け取って行動する人たちが原理主義者と呼ばれていることも知っている。キリスト教徒や仏教徒の多くは世俗道徳に反する教義を主張していないので、私たちは彼らと問題なく付き合うことができる。それは彼らが”本物”の教徒で原理主義者たちが”偽物”の教徒であるわけではない。解釈が違うのであり、ただ世俗道徳を尊重する教徒が多数派なだけだ。同じようにイスラム教徒だけ本物だの偽物だのと言うこと自体がナンセンスである。もちろん世俗的なイスラム教徒自身がISISと一緒にされないための自己防衛のため主張した側面はあるだろうし、それは理解できるのだけど。*1
とはいえ、じゃあ”一般的”で”多数派”なイスラム教徒はどんな規範を持っているのだろう。キリスト教徒や仏教徒のように、教義よりも世俗道徳を重視しているのか、それとも原理主義により近く、宗教的な規範を維持しているのか、そんな疑問を強く思った。道路上で礼拝する大量のイスラム教徒の写真なんかを見かける限り、彼らが西欧的な世俗道徳に取り込まれているようにはとても見えなかった。
池内恵や中田考の著作を読んでみてわかったのは、多くのイスラム教徒たちはISISほど極端ではないにせよ宗教的な規範を強く維持していて、自由主義や平等主義や人権思想に反する考え方を持っているということだ。世俗道徳に骨抜きにされた宗教とは比べ物にならないほど、イスラム教の教えはイスラム世界に対して強い影響力を持っている。(もちろん世俗道徳に親和的なムスリムが多数いることは否定しない)自分はイスラム社会の専門家でもないし、彼らの発言を鵜呑みにしてると言われればそれまでなのだけど、立場が大きく異なる2人が揃って同じ主張をしていることや、現実に起こっている移民問題などを見ていても説得力があるように感じている。*2
規範の大きく違う人間同士が共存することは難しく、様々な問題を生む。移民を受け入れたEU諸国は多様性のもとにイスラム教徒の価値観を尊重し、それは自由や平等を尊重する規範意識をもつ国民に大きな反感を植え付ける。とはいっても共存できない価値観が衝突したら取れる選択肢は同化と排除以外にないわけで。もちろん多くの人は好んで排除なんかしたくないので、彼らが同化することを期待する。自分もそうやって移民の人たちが我々の世俗道徳に同化することを期待していたわけだけど、現実はそんなことは全くなくて未だに移民と原住民の対立はニュースになり続けている。
自分は強い信仰と、内面化された規範を近いものだと考えている。私たちは合理的な場面ですら嘘をつくことに罪悪感を覚えるし、暴走したトロッコを止めて5人の乗客を救うために1人の太った人間を犠牲にすることを直感的に間違っていると考える。例えば自分は、敬語なんてなくなってしまえば良いと考えているにもかかわらず、見ず知らずの相手に敬語を使われないと瞬間的に不快感を感じてしまう。一度内面化された規範意識は私たちを強固にしばり、それを用いることが非合理的な場面ですらその規範に従ってしまう。
同じように強い信仰は、それに対して後天的にどれほど疑義を抱こうと、その信仰がどれだけ自分に不利益になろうと、簡単に振り切れないものであるのだろうと考えている。内面化された規範に歯向かうと不愉快なように、信仰に背くと不愉快になるんだろう。そして人間は直感的な感情に主導権を握られていて、理性はその奴隷として動いてしまう。*3
どれだけ多様性を尊重したとしても、自由や平等を否定する価値観を私たちの世界に持ち込むことは許容できないわけで、信仰であり内面化された規範を説得して変更させるしかないわけだとは思うのだけど、それはとんでもなく難しくて遅々とした作業なんだろう。そしてその実態は身も蓋もないパワーゲームになるしかないと思っていて、自由や平等を尊重することで幸福になるように仕向けて、世俗倫理に反する宗教的な教えに従うことで不快になる社会を作っていくことになるのだろう。あまりにも身もふたもなさすぎて多様性ってなんだっけみたいな絶望的な気持ちになるのだけど、とにもかくにもそれ以外の解決はないんだろうなと考えている。
動物倫理とヴィーガンと肉を食べるのをやめられないだろうということ
動物倫理とは動物の権利についての倫理である。ざっくり説明すると、動物(あるいは苦痛を感じる能力を持つ存在)は人間と同様の配慮を受けるべきである。他の存在と比較して人間を特別扱いし、特権的な扱いを行う根拠はなく、それは種差別的な発想であって、功利主義に基づき是正されるべきである、という考えから生まれた倫理だ。ピーター・シンガーが著書で主張して広まった。
自分はシンガーの書籍すらちゃんと読んだことがなくて、それを紹介するサイト経由でこの動物倫理に触れている初学者未満の人間なので詳細は割愛します。というかその能力はないです。ちゃんと知りたい人は以下のサイトを見るといいと思います。(何よりシンガーの著書を読むのが一番いいのだろうけど俺もまだ読んでないので・・・・・・)
いろいろ考えてみた結論として、シンガーらが主張している動物の権利についての考え方は、自分にとって非常に説得力がある。シンガーらが主張するように、肉食をやめてヴィーガンとして生きることがより倫理的であると考えるし、種差別は是正されるべきであると考えている。もちろん動物倫理的な思考を実社会に落とし込もうとすると色々と考えなくちゃいけないだろうし、弊害もあるだろう。例えば経済的に恵まれている人間のほうがヴィーガニズムの実践は容易だろうし、それは裕福であること≒倫理的みたいな風潮を助長するのかもしれない。でも理念には賛同しているわけだし、問題があることはベターを目指さない理由にならない。やろうと思えば俺はヴィーガニズムを実践して肉を食べるのをやめることができるだろうし、どう考えてもそのほうが倫理的であると考えている。
なのにそれなのに、俺は全く持って肉食をやめられる気がしない。なんでだろうとずっと考えていたのだけど、それは俺が「動物の権利」という規範を全くもって内面化できていないからなのだろう。理屈でどれだけ肉食を悪と考えたとしても、肉食に付随する罪悪感と肉食への欲求を天秤にかけると後者が圧倒的に勝ってしまう。そのうえ、自分が好意を抱いている人たちの多くは肉食をするし、その人たちは「あなたたちは肉食をする差別主義者だ」と言われたら不快に思うだろう。もちろん自分は好意を抱いている人たちに嫌われたくはない。端的にいって、肉食をやめることによって自分が幸せになれない。
もちろんこれは直近の話であって、将来的に変わってくるのだろうとは思う。代用肉や動物倫理的に問題のない培養肉の味や価格が現在の動物肉に近づくにつれて、これまで行われてきた肉食は非倫理的なものとして一般に非難されるようになると思っている。そうなれば自分も肉食をする理由がなくなって肉食をやめるのだろう。一度理屈として納得できた倫理は徐々にではあるけども内面化されていくという経験則があるので、もしかしたらテクノロジーの進歩を待たずとも10年、20年先には肉食をやめているのかもしれない。なんにせよ、時間がたてば自分の規範と行動が伴うのだろうと楽観視している。
でもこの考え方って経済合理性ゆえに奴隷制を支持するのと大差ない思考様式だよなーと思うのだけれども、そこまで考えても肉食をやめようと考えられないのがすごいなというか、規範化されてない倫理観のどうしようもない弱さみたいなのを考えてしまう。
ということで規範を内面化しないとどうにもなんなくてモヤモヤするよねという話を引き延ばすとこうなりました。でも自由意志だのなんだのを強烈に内面化している自分にとって他人の規範をどうこうするとかそういう話自体を強烈に忌避する気持ちもあり、人間はままならないなということで雑にまとめます。考えがまとまっていないしまとまる気がしない。